私は学生時代から歴史が好きでした。

読み物としても学校の科目としてもです。
最近、そんな歴史についてお金の知識を踏まえて(より具体には金融や財政の観点を加えて)見直すともっともっと面白いことを知りました。
例えば歴史では様々な出来事、例えば「○○の改革」や「○○戦争」を習います。
さて、これらの出来事の直前がインフレだったのかそれともデフレ基調だったのか?
或いは当時の金融政策はどうだったのか。

緩和してたのか、
それとも緊縮財政だったのか…等々
お金にまつわる、言い換えれば金融経済の情勢・状況があるはずです。
今考えてみると教科書の記述って唐突に「この時代の生活は苦しく…」とか始まったりしますが、その理由はほとんど触れられていなかったと思います。

勿論歴史の先生(或いは教科書編纂する学者)に
金融経済の見識まで求めるのは大変かもしれません。
でも歴史ってそんな視点での捉え方も必要な気がしますし、むしろその視点がないと見誤ることもあると考えます。

取敢えず私自身の体験だと学生の頃には良い施策と感じた
「質素倹約を推進した○○の改革」、
一方イメージの良くなかった「改鋳(大判小判の金銀成分減らす)」
とか公共工事に積極的だった例えば田沼章次さんの評価が、
自分の中では180度変わりました。

当時は、節約してんのになんで幕府財政は
よくならんのやーとか思ってました…。
恥ずかしい…。
金融政策や財政政策、GDPの概念やマクロ経済の基礎と絡めて歴史を学べればより深い学びとなるはずです。

また個人の財布と国家の財政という関係性1つ取り上げても、
合成の誤謬という概念を学ぶにはとても良い教材ですし、
現在の日本政府の国債発行の話なんかも絡めても良いと思います。

その際は、日本の借金、国民1人当たり、、、みたいな、
トンデモ話を鵜呑みしないようにしないとな!
ここまで書くとむしろ金融や財政を知らずに歴史を学ぶって(特に中世以降)相当もったいないというか、危険というか、そんな気がします。
本当の意味で歴史を学ぶにはお金、経済にも見識が必要です。

出来事丸暗記のテスト対策なら良いですが、
何故それが起こったか何故それを実施したのか
何故そんな機運が社会に広まったのか、、、
そんなことを考えるのが本当の歴史の勉強な気がします。

私これでも経済学部経済学科だったんですが、
今更ながら…。
そうそう、私の好きな言葉があります。
“愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ”
歴史を賢く学ぶにもお金の教育は必要のようです。

子供が中学高校生くらいになったら、
教科書見ながらそんな視点を一緒に
考えられるといいなと思う今日この頃です。






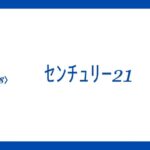
コメント